最終更新:
![]() mototemplate 2021年12月02日(木) 19:07:55履歴
mototemplate 2021年12月02日(木) 19:07:55履歴
【インタビュー:萩尾望都・藤本由香里】2000年12月20日
「少女まんが魂(188-206ページ)」のインタビュー
「少女まんが魂」現在を映す少女まんが完全ガイド&インタビュー集
著者:藤本由香里
発行日:2000年12月20日
出版社:白泉社
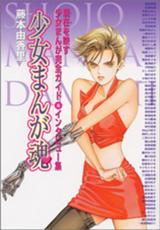
ロングインタビュー
萩尾望都
(図版に続いてテキスト抽出あり)










ロングインタビュー
萩尾望都
どんな関係であっても、人間関係はいつも混迷で、時々ほんの一瞬、いい事があるだけ。それでいいじゃないか、って
逆インタビューではじまる
藤本 今日は、なにか、萩尾さんのほうからも私に質問があるという(笑)。
萩尾 ええ、まんが家は質問されるばっかりだから、たまには質問してみたいなっていうのと、藤本さんのまんがの評論を読んでいると、藤本さんっていう人が、非常に面白いなあと思って。
藤本 あッ、ありがとうございます。とても光栄な事なので、じゃあ、まず攻守を逆にして、萩尾さんのほうから……
萩尾 はい。じゃあ、いいですか? 私がいつも聞かれるのは、「いつ頃からまんがを描き始めたか」とか「読み始めたか」とか。なんかパターンなんですけど、それからお聞きしていいですか?
藤本 はい。私はあんまり絵が上手じゃないので、「まんが家になろう」と思ったことはないんですが、読み始めたのは、手塚治虫さんの『リボンの騎士』が最初なんです。
父親の散髪についていったのがきっかけで、父親が散髪している間に、なんかそこの床屋さんに『なかよし』が三冊ぐらいあったんですよ。それで、読み始めたらもう止められなくなって、夢中になって読んでて。
でも、男の人の散髪って、すぐ終わるじゃないですか。だから、父親が「帰ろう」って言ってるんですけれども、とにかく「ちょっと待って、ちょっと待って」。そしたら床屋のおじさんが、「いいよ、それ、おじょうちゃん持って帰って」。もう天にも昇る心地でしたね。それが一番最初です。
それから「まんがって面白いものだな」と思って、なんか近くに貸本屋さんがあったもので、そこにとにかく通って。
萩尾 貸本屋さんで借りたのは、当時の「赤本」っていう単行本なんですか? それとも 普通の雑誌?
藤本 単行本と雑誌と両方、借りてました。ただ、あんまり借りてくるもんで、母から禁止令が出て、「月曜日に一冊だけ借りていい」っていうふうに決まったんですね。だから、読めるのは月に四、五冊。
萩尾 月曜日に一回、一冊だけ?
藤本 ええ。あと、かわいがってくれていた大叔母が、『なかよし』は買ってくれてたんです。で、その頃、貸本屋で借りてくるまんがはほとんど少年誌を読んでました。
萩尾 えッ、ちょっと待って。『なかよし』の次に少年まんが誌を読んでた?
藤本 はい。ちょっと変なんですけど、考えてみると、やっぱり手塚さんに惹かれてたんだと思うんです。その頃、『少年』とか『ぼくら』とか『少年画報』『少年ブック』とかあって、そこに『ふしぎな少年』とか、『鉄腕アトム』とかが連載されてたんですよ。たしか少し後に『ビッグX』とか。ちょっと年代はわからないんですけれども。
だから、そういった少年月刊誌をだいたい借りてて。あと、たまに『りぼん』を読んでいましたね。やっぱり、なんか『りぼん』のほうが、ちょっとお姉さんらしい感じが、その当時あって。
萩尾 はい。そうですね。
藤本 だからむしろ、『りぼん』を毎回読むっていうよりは、『ぼくら』とか『少年』を読むほうが当時は面白かった。で、あとは今村洋子さんとかの単行本を借りてました。
それからほら、叔母の家に行ったり、祖母の家に行った時っていうのは、「何か買ってあげようとか」とか言われるじゃないですか。 そういう時、貸本屋さんでまんがを借りたい、っていうのがその頃の一番の願いだったので、遊びに行くたんびに、そこの近くの貸本屋さんで何冊か借りていた。そういうことの積み重ねで今まできました。
萩尾 えっ、一人っ子ですか?
藤本 いえ。四人兄弟です。 萩尾さんと同じですよ。 私は一番上ですけど。
萩尾 あッ、長女なんですか。じゃあ、お姉さんが一冊借りて読むと、下の兄弟がそれを読む。
藤本 ええ。そうですね。
萩尾 あの、妹さんもいる? それともご兄弟ばっかり?
藤本 いや、すぐ下は弟で、あと妹、弟ですから、女、男、女、男っていう順序なんです。だから、下の子たちはほとんど少女まんがを読んで育った。私が少年まんがを読んでいた頃っていうのは、まだ下の子が生まれていなかったり、小さかったりしましたから。
萩尾 ああ。じゃあ、小学校の低学年の頃ですね。それだと。
藤本 そうですね。最初に読んだのが五歳ぐらいですから。それから小学校四、五年くらいまで、男の子のまんがを読んでました。でも、あの頃、少年月刊誌って次々に休刊になっていきましたよね。
萩尾 そうですね。うん、うん、うん。
藤本 それで、私も十歳くらいになってくると、だんだんなんか女の子のまんがのほうが面白くなってきて。で、それからは、別冊マーガレット』とか、『りぼん』とかも読み始めて。『なかよし』はずっと続けていたんですけれども。それから「週刊マーガレット』とか、別冊少女コミック』とか、『週刊少女コミック』とか、そちらのほうに行ったんです。
萩尾 ああ、本当に大量のまんがにうもれて育ってきたんですね(笑)。
藤本 その通り(笑)。だから、下の子たちに、少女まんがの影響がすごく強くって。うちの弟のところに女の子が二人いるんですけど、その名前が「さくら」と「更紗」っていうんですよ(笑)。
萩尾 凄い。
藤本 私はその名前を聞いた時に、いやー、これは私が思っていた以上に少女まんがを読ませた影響は大きいかもしれないって(笑)。
萩尾 弟さんがつけられたんですか?
藤本 そうなんです。
萩尾 えー、本当? でも、更紗っていう主人公のまんがってありましたっけ。さくらはよく聞いたけど。
藤本 ええ、田村由美さんの『BASARA』の主人公が更紗です。ちょうど連載が始まった前後かなぁ、更紗が生まれたのは。もしかしたらそれよりはちょっと前かもしれないけど……でも、そういう特定のものからとったっていうよりはーー
萩尾 イメージ。うん、なんか。
藤本 そう。イメージがやはり、少女まんが的感性なんじゃないかなと思うんですよね。
藤本、「家庭内文化大革命」 を体験する
萩尾 そうなんですか。あの、私ねぇ、藤本さんの評論を読むとね、なんかこう「すごく優等生で、頭のよい人だなぁ」っていう印象が強いんですけど。
藤本 そうですかぁ。
萩尾 あんまり、親に心配掛けないタイプっていうか。
藤本 いや、優等生って、そういう意味だとすると、ちょっと違うかもしれない。たしかに学校の成績とかはよかったんですけど、いわゆる「優等生」っていう言葉で括られるようなよい子だったっていう感じは、自分ではしないんですね。 私の自己認識では、かなり内気な子で、わりと「萩尾さんもそうだとうかがってますが、まわりから「変わってる、変わってる」って(笑)言われるこどもでしたね。
どっちかっていうと、「夢見がちな少女」っていうようなところが多かったんじゃないか なぁ、という気はします。
それからなんというか、ちょっと成績がよかったりしたことで、もう、すごい違和感があるっていうか、それで周りの不興をかったり、ちょっと意地悪されたことが、小学校の五年生くらいからあって。
萩尾 なんか、この頃のいじめって、成績のよい子がいじめられるんですって。その類いなんですか?
藤本 そこらへんになると微妙なんですけど、自分でもすごい罪悪感があって。それに、親も成績がいいっていうことを評価しない。むしろマイナス。
萩尾 うーん、えぇ? そうなんですか?
藤本 ええ。とくに父親から、なんか「人間的に欠陥がある」みたいなことをけっこう言われて……。
萩尾 ふーん、それは、ちっちゃい頃から?
藤本 ちっちゃい頃から。
萩尾『なかよし』、もらってきたから?
藤本『なかよし』(笑)、もらってきたからじゃないんですけど、簡単に言うと、うちの父親って社会主義者なんですよね。共産党員じゃないんだけど、学生時代に大学の学生運動の書記長かなんかやってて。
萩尾 あぁ、すごい。なんとなく……うーん、はい、真面目な人なんだ。
藤本 ええ。それで、運動系の言葉に、「自己批判せよ」っていうのがあるでしょ。
萩尾 ありますねぇ。
藤本 あれをこどもに対してやるんです。なにかというとそんな感じで本気で批判される。まだこどもなのに(笑)。しかも不幸なことに私が、自分が何を言われているのか理解できるこどもだった(笑)。
あとで考えてみればちょうどその頃、日本共産党の査問があったり、中国の文化大革命が起こったりしてた時で、私は今になってそれを「家庭内文化大革命」って呼んでいるんですけれども。『イワンの馬鹿』とか読まされて、お前は民衆の敵だって。
萩尾 そんなー。でも、お母さん、かばってくれませんでした?
藤本 いやぁ、かばってくれませんでしたね。
萩尾 お母さんも、自己批判してたのかしら。
藤本 (笑) うん。母は母で、ちょっと違う感じで激しい人だったんで。
四人こどもがいますでしょう。でもずっと働いていたんですよ。学校の先生だったんですけど。
萩尾 あぁ、学校の先生……。
藤本 ええ。で、忙しかったせいもあるんでしょうけど、なにかというと怒鳴られるとか、手が飛んでくるとか。
萩尾 学校でもそうだったの? お母さん?
藤本 学校では、そんなにぶったりしてないと思うんですけど。でも、あの、校内暴力がすごくなってた時、ありましたよね。あの頃、母は実業高校の先生だったんですけど、授業をしている時に、三年生の男の子の一人があんまりうるさいんで、「出て行きなさい」って言ったらしいんですよ。するとその子がすぐ出ていった。そしたら、「なんで出て行けって言われてすぐ教室を出ていくのか」って言って、高校三年の男の子に平手打ちをくらわしたらしいんです(笑)。
萩尾 うそー(笑)。
編集者 強い(笑)。
藤本 私もさすがにそれを聞いてびっくりして、こどもの頃、自分がけっこうビシビシやられて育ったのも、「こういう人だったらしょうがないかな」みたいな感じを持ちましたけどね。
萩尾 豪傑。豪傑っていうか、凄いねぇ。うん。
藤本 ただ、当時はやっぱりそういうふうに怒鳴られたりするのは嫌だった。落ち着かないし。
父のことにしても、そういう家族体験っていうのは、相当トラウマになっているなと、自分でも思う。
萩尾 いや、でも、お母さん、学校の先生していて、一日中、生徒を相手に授業をしてきて、家に帰って四人こどもがいるって、それはヒステリーも起こすかもねぇ。でも、こどもは大変ですね。
藤本 ええ、こどもは大変ですよ。大きくなってからは、ああ、父親は別に家事する人じゃなかったし、母も余裕がなかったんだろうなあ、とわかるんですけどね。だけどやはりこどもにしてはかなり厳しい体験だったし、そうすると、「自分は本当にこの世に存在していてもいいのだろうか」って、思い始めるわけですよ。その頃のそういう気持ちに、そのころ萩尾さんのお描きになっていた少女まんがが、こう、すーっと入ってくるっていうのか、すごく救われたという気がしました。
萩尾 そうかぁ。私、藤本さんの『私の居場所はどこにあるの?』っていう評論を拝見して、お会いすると美人だし、頭もいいのに、でもずいぶん何か迷いっていうか不安感があるんだなあ、って。今うかがってて、そういう女の人って多いのかなあ、って思っちゃいました。
異端の存在を描くということ
藤本 ええ。でも、萩尾さんご自身はどうなんでしょう? 四人兄弟の二番目でいらっしゃるんですよね。
萩尾 そうですね。まぁ、うち、だんご四兄弟(笑)だったんですけど、上と下がちょっとおっとりしていて、真ん中の二人が、ちょっと性格がきついっていうか。挟まれるとそうなっちゃうかなっていう、自分でもその諦めがあるんですけれど。
藤本 えーと、一番下が弟さんで、上三人が女の子でしたよね。仲のよいご兄弟だったんですか?
萩尾 いや。すごい仲悪かったんですよ。でも中学校の頃、まんがなんか読んでいてもわりとみんなアットホームでしょう? 今村洋子さんのまんがとか。だから、こんなに仲の悪い兄弟なんて世界中でうちだけだろうなとか思ってましたよ。でも、成人して各自家を出ていったら、なんとなく仲よくなりましたけど。
藤本 それぞれ幾つくらい違うんですか?
萩尾 二歳、二歳、二歳、えーと、最後は四歳か。
藤本 私のところは、二、三、三、なので、だいたい同じようなものですね。一番上のお姉さんが、たしか小夜さんとおっしゃるんですよね。『小夜の縫うゆかた』っていうのは、お姉さんがモデルなんですか?
萩尾 いや、名前だけ借りたんですよ。
藤本 そうですか。……萩尾さんの作品っていうのは、母殺しの作品が多いっていわれてますよね。初期作品もだけれど、最近の作品でも、『メッシュ』とか『残酷な神が支配する』とか。どこかで萩尾さんのお母様もうちと同じく厳しかったっていうようなこともお書きになってますよね。
でも、萩尾さんの作品を拝見していると、やっぱり、「うちの親子関係とは違うな」って感じがするんですけど。
萩尾 うーん。「自分は存在していていいんだろうか」っていう問いはね、それこそ、私も中学校のころずっと悩んでいたんですけれど、心理学者なんかにいわせると、それは、物を考える人が思春期に必ず通る成長過程の一つのパターンだっていうんですね。
中学校の頃は、まわりに誰も相談する人はいなかったけれど、成長して他の人に話してみると、「いやぁ、私もそうだった」っていわれる。やっぱり成長して自我を確立していくっていうのは大変なことなんだなあ、と思いますね。
『ポーの一族』を描いた時にも、主人公は吸血鬼だったんだけど、あれは要するに、世の中の生態のルールから全く外れたものが存在している時に、では私たちはどうやって自分たちの存在を確認するのかというので、あのキャラクターを設定したんです。するとけっこう、共感してくれる読者がいる。あの時は、「どこが受けたんだろう」じゃないけど、不思議は不思議だったんですね。でもお話をうかがってると、やっぱり皆、存在の不安みたいなものを抱えているのかな。
藤本 ええ。でも、萩尾さんが「変わってる」と言われていたとか、あるいは、異端のものを描こうとする、その異端の感覚っていうのは具体的にはどんな感じなんですか?
萩尾氏マネージャー 私、一つ例、いっていい?
藤本 ええ。どうぞ。
マネージャー たとえば、クラスメートがタレントの話をしてるとしますね、今だったら、ジャニーズ系とか。すると萩尾さんはそれに興味がないから、それで話が盛り上がっている時に「それよりさぁ、SF読んだ」って答えるの。
藤本 (笑)。
萩尾 と言って、嫌われていた人(笑)。
藤本 でも、そこで「SF読んだ?」って割って入れるっていうところが、やっぱ、萩尾さんの健康さって言うか、強さだと思うんですよ。聞いているとなんか、私もたぶん似たような位置どりだったと思うんですけど。つまり、アイドルの話とか、あるいはテレビの話とかで、皆が盛り上がっているのに、なんか違和感がある。うまくそのリズムに入っていけないんですね。たぶん何かリズムが違うんです。ものを考える時の。
萩尾 そうですねぇ、リズムねぇ、うん。
マネージャー だから、昔はねぇ、私が「開放的自閉症」って言ってたわけ。
萩尾 あぁ、そうそう「明るい自閉症」って(笑)。なんで、自閉症っていうのかって言うと、これは、まあ、ギャグで使っているんですけど、要するに対人コミュニケーションにズレがあるっていうんで。
藤本 その時に萩尾さんのその明るさって、どこからくるのかな。私なんか、「自分が悪いんじゃないか」と思っちゃうんですね。「家庭内文化大革命」を経てきたからかもしれないけど。
マネージャー 私、思うんですけど、藤本さんは意外と他の人のこと考えているじゃないですか、ちっちゃい時から。でも、萩尾さん系統の人は、他の人の事情や都合をうまく考えられないんですよ。自分で精一杯だから。
藤本 (笑)。
マネージャー 萩尾さんは自分のことをまんがに描いて、それに共感する人が「先生なら私のこと、わかってくれますよね」ってファンレターをくれるけど、でも、どちらも魂の孤独はあるんですけど、じつは自分のことで精一杯。それが共感をよぶシステムなんですよ。萩尾望都の。
藤本 でも、なんか萩尾さんは基本的な所では、やっぱり支えられているというか、実は、かなりいいご両親だったんじゃないかなっていう気はするんですけど。そんな事はない?
萩尾 いや、あなたの話を聞いてると、うちはよかったんだなぁと思う(笑)。
藤本 (笑)。そうですねえ。たとえば最近、よく「アダルトチルドレン」って言葉を聞きますけど、萩尾さんなんかは、自分はアダルトチルドレンだって思いますか?
萩尾 うーんとねぇ。思います。
藤本 えっ? 思います?
萩尾 はい。 思いますね。
藤本 どういうところで? 私、「思わない」っておっしゃると思ってたんですけど。
萩尾 いやぁ、私、橘由子さんの『アダルトチルドレンマザー』っていう本、面白かったんです。お母さんがあまりにも立派で管理的なために、どんどんこどもが自信をなくしていくっていう。ああいう感じは非常によくわかるし。つまり、親が決めた「あなたはこんなふうにやりなさい」っていう規範に従えないでいる自分をやっぱり責めるわけですよ、悪い子だって。そういう状態が、三十歳まで続いているから。
三十歳の時の大ゲンカ
藤本 というと、三十歳の時に、何か転換があった?
萩尾 大喧嘩があって。
藤本 (笑)。たしかまんが家になる時も反対されたんですよね。それは、お父様の反対だったんですか? お母様は、金賞をとったらあんまり何も言わなくなったと書いてらっしゃいましたけど。
萩尾 母のほうは、まあ、勉強の邪魔になるっていうので反対でした。それから、やっぱりまんがっていうジャンルがわからないもんですから、「変なことをしてる」と思って拒否してたんです。で、父親のほうは、要するに、「そのうち止むだろう」と思ってるわけです。ですから、金賞もとって、お金をもらったことで、とりあえず家でまんがを描くっていうことは許してもらったんですね。ところが、やっと上京してまんが家になることになって、着々とプロの道を歩んでましたら、三十歳近くになって、「そろそろ止めたら」っていう話になって(笑)。
マネージャー 昔の人だから、価値観が「女性は、結婚して一人前」。それから、萩尾さんは当事者だからわかんないと思うんですけ ど、はたから見ると、この人のお父さん、非常にユニークな人ですよ。
萩尾 (笑)。
マネージャー この変さは、お父さん譲りです。萩尾さんのお父さんはですね、本当に珍しい人です。一種の天才気質なんだと思うんですけどね、村では生きにくい。
萩尾 (笑)。父親も、あの、対人対応力っていうの、ちょっと欠けてまして。そのぶん、何か、ちょっとすっとんだような人なんですね。
藤本 えっ、どういうふうに?
萩尾 なんか、あのー、過剰に他人に対して親切にしようとする。本人に悪気はまったくなくて、周辺の悪意も信じない人なんですけど、やっぱりTPOが悪くて、迷惑する時もありますよね。そう言うと、こちらが好意でやっているんだから、向うが喜ぶのが当然であって、それが迷惑だっていうのは、その人がおかしいんじゃないかって言うんです。
藤本 それはあの、『感謝知らずの男』で、 凄い親切な隣人(笑)っていうのが出てきますけど、あれって、なんか、反映されていますか。
萩尾 はい。あれは父を観察したモデルです(笑)。
藤本 でも、ある時期までは理想のお父さんだったんでしょう?
萩尾 そうですね。うちは、母親がきついぶん、父親は、非常に優しい人でした。
藤本 それで、三十歳の時の大喧嘩っていうのは?
萩尾 あの頃は、ちょうど父が退職した頃で、私のほうは単行本が毎月出始めた頃だったものですから、税金の申告なんかが大変になってしまって、それで、会社組織にして父に会計をやってくれないかって頼んだんですよ。でも、まんが家の仕事場ってのがよくわかっていなくて、私が一種、お絵描き教室をやってると思っている。だから、アシスタントさんが来て、手伝ってもらってお給料渡しますね、そうしたら、「なぜ、お弟子さんにお金を渡すの? 普通はね、お弟子さんが先生に持ってくるんだよ」って。
藤本 なるほど。
萩尾 そういうのから始まって、本当に一事が万事、ズレていくんです。説明すると「ああ、わかったよ」って言うんだけど、また翌月、払う段になると同じことを言う。
藤本 (笑)。はい。
萩尾 で、当時は、ちょっと狭い家に住んでいたもんですから、仕事中に父が上京してきても寝る場所がない。とくに締切りが重なっちゃいますと、「ホテルに泊まって」というわけです。すると父は、それは嫌だ、「わざわざ上京して娘のところにきたのに、なんで親が旅館に行かなきゃいけないんだ。アシスタントさんたちをそっちに泊まらせなさい」。そんなことはできないというと、お父さんがくる間は仕事休みなさいって。
藤本 マイペースなんですね、とにかく。
萩尾 まあ、そうですね。そして帰ってから母に、娘の家にいったら旅館に泊まらされたとか、仕事でろくに話ができなかったとかっていうわけです。すると母が怒って「仕事なんか止めてしまえ」。それでどんどんこじれていったんですね。
藤本 はい。それで結局、最後の爆発が起こったと。
萩尾 ええ。「もう、私は会社を潰します」って言って。
藤本 それでどうしたんですか?
萩尾 社長は父だったんです。だから私はクビになりました。
藤本 (笑)。それはかなり尾を引いたんですか?
萩尾 ええ。その後、三年くらい口をききませんでしたね。
「まんが家をやめて童話作家になりなさい」
藤本 その大喧嘩がちょうど三十歳ぐらいだというと、ご両親には、もうそろそろ仕事を止めて結婚しなさい、っていうのがすごくあったんですか?
萩尾 それもあったみたいですね。母も、父も。要するに、もうお金もできたし、名前も知れたし、そろそろまんが家をやめたらどうかと。とくに母は、まんがっていうものがまったくわからないし、好きじゃないから、「お母さん、親戚の人に娘がまんが家ですっていうのは恥ずかしいから、童話作家になんなさい。童話作家だったらいいから」って(笑)。
藤本 それもすごい(笑)。
萩尾 趣味で描いてればいいんじゃないのって。
藤本 いや、なるほどね。でも、その頃っていったらもう、『ポーの一族』とか、『トーマ の心臓』とか出てて、萩尾さん、ものすごく有名になってますよね。
萩尾 でも両親は、出版界とは関係のないところで生活していますから。
だから私が「いや、まんがやめたら、いったいどうやって食っていけっていうの?」と言ったら、「テレビとか新聞に出ればいいじゃないか」(笑)という恐ろしい答えが返ってくるという。うーん。「もう、こういう人とは話したくない」って。
藤本 でも、萩尾さんはまんが界だけで有名だったわけじゃなくて、それこそ新聞とか、そういうメディアでもとり上げられてましたよね。それを見て、「立派な仕事してるんだ娘は」っていうふうにはならない?
萩尾 実は私も、母がまんがを嫌いだったけれど、ああいうメディアに出てれば、そんなふうに考えてくれるかな、と思ってたんですよ。だから依頼が来ると、仕事の合間にちょっと出てたりしたんですけど、結局、まったく理解には遠かったんだっていうことがよくわかりました。
マネージャー 結局、描いてるまんががもとで有名になったと思ってなかったんですね。
藤本 ああ、そうか。お父さんやお母さんにとっては、逆に、テレビに出たり新聞に出たりするから有名なんだ。だったら人聞きの悪いまんが家(笑)なんかやめて、そっちで食べていきなさい、と。
こどもの混沌状態を描くのが面白い
藤本 私は、萩尾さんの作品は『なかよし』にお描きになったデビュー作、『ルルとミミ』から、ずっとすごい好きで、『ケーキケー キ ケーキ』とか。あれ、別冊付録でしたよね、私の記憶では。
萩尾 そうですね。はい。
藤本 でも、その後、『少女コミック』のほうに移って、ぜんぜん作風が変わった。でも逆に、その頃から萩尾さんの魅力がどーっと開花したっていう感じがして。
『ポーの一族』や『トーマの心臓』ももちろんだけれども、当時、『塔のある家』とか 『キャベツ畑の遺産相続人』とか大好きだったんです。あのへんの作品は、なんていうのかな、「こどもの頃生きていた空気」みたいなものとすごく結びついていて、読むとその頃の感情っていうのがどーっと蘇ってくる感じがするんですよね。
萩尾 こどもの感覚、こどもの考えていることっていうのには興味がありますね。やっぱりこども時代の一日一日っていうのは、毎日毎日、発見につぐ発見の連続ドラマなんですよ。これまで知らなかったことを知って、また知って。前に知ってたことと次に知ったことが結びついて、っていうぐあいに、非常に目まぐるしく変わっていく。けれど同時に、そんなふうにして知る世界は断片的だし、力もないし、いろんなことを考えるんだけど、どこに向かってそういうものを話せばよいのか、形にしていけばよいのか、わからないでいる。その混沌状態がすごく面白い。
藤本 ほんとに混沌状態ですよね。
萩尾 で、選んだジャンルが少女まんがだったせいもあって、ちょうどその時代を思い出しながら描くのがね、けっこう快感なんですよ。
『残酷な神が支配する』と人間の混沌
藤本 萩尾さんは、デビューなさってからもう三十年くらいになりますよね。そうすると、萩尾さんのこども時代と今のこどもとはずいぶん変わってると思うんです。それで、萩尾さんの場合は、自分のこども時代に常に帰っていって、それを作品を描く原動力にしているのか、あるいは、もうちょっと今の時代を生きるこどもと意識をシンクロさせていくことで作品が生まれてくるのか、そのへんをうかがいたいんですが。
というのは、今お描きになっている『残酷な神が支配する」。この作品は、今まで萩尾さんが描かれてきた親子の問題とはまた、何か一つ違うところにいってますよね。 始まったのがちょうど、ささやななえさんの『凍りついた瞳』など、社会的にもチャイルドアビ ューズ(こどもへの性的虐待)への関心が高まってきた頃ですけど、そういうことと関係があるのかどうか。それからこの作品では、こんなハードな体験、っていうか、息苦しくて、なにもここまで……っていうような世界にまで入ってきますよね。萩尾さんがどうしてこういうテーマをお選びになったのか。
萩尾 あのテーマを選んだいきさつは色々あるけれど、描きながらけっこう自分でこだわっている部分っていうのは、自分が過去に失敗した人間関係です。
直接的な話じゃないですよ。でも、それを形を変えてずいぶん入れてるっていうのがあります。こんなふうにすると失敗するとか(笑)。
藤本 たとえば?
萩尾 うーん、三十歳で親子喧嘩した話とか(笑)。人に何かを話してわかってもらう、自分の気持ちを伝えるってことって、本当にむずかしいなっていう.……
藤本 なるほど。具体的に作品にそくして言うと、たとえばイアンの行動。萩尾さんはどこかで「イアンの行動っていうのは間違っている、だから皆さん、ああいう真似をしないように」っておっしゃってましたよね。端的にいって、イアンの行動はどこが間違っているんでしょう?
萩尾 なんかね、その話をすると、舞台裏になって、また話も長くなっちゃうんですけど。人間ってね、あのー、またうちの父の例を出してすいませんが(笑)。
藤本 (笑)。はい。今日はお父さんシリーズ。
萩尾 たとえば、自分がよいと思ってやったことなら皆が感謝するはずだ、というあの間違ったセリフ。そういうものがあったりするわけですよ。だからたとえば、イアンがジェルミを迎えに行って、引き戻して更生させようとしてますが、あれは余計なことです。言ってしまえば。
藤本 でも、普通に考えて、ジェルミが男娼になってクスリまでやってるという状態をみると、やっぱりなんか、手を出したくなるじゃないですか。 私だって手を出したくなると思う。
萩尾 うん。そう、そう。だから、あれはね、手を出したくなった人が不幸になるというパターンを描いているの。
描き手の私としては、イアンが正しい事をしてるって意味で描いてるわけじゃない。この人の性格だったら、こんな事するだろうと思ってやってる。でも、読者によっては、そこを一緒にしちゃうわけですよ。だから、その時に、「あのう、皆さん、イアンが正しい事をしてるとか、思わないようにしましょう」って、その人のために言ったんです。
藤本 あぁ、そうか。ではどうするのが正しいんでしょうか?
萩尾 それがねぇ、正しい道っていうのはないんですよ。人間関係においてはね、まずくてもやらざるを得なかったりね。でも、そうやってるなかで別の解決法が見つかったりすることもあるんですけどね。
藤本 主人公のジェルミは、いろんな傷をもう一度繰り返しながら行きつ戻りつしてますよね。あれを見てると、やっぱりあれだけの体験を乗り越えるのには時間が掛かるんだな、というのはすごく伝わってくるんです。
だけど一方で、リンドンがイアンに、ジェルミがどんな状態になっても「そのまま落としておきなさい。手を出すな」って言うじゃないですか。で、「あなたは何度も彼を裏切っているんだから、彼があなたを信じると思うのか」みたいなことを言う。それは正しいんだけど、でも、やっぱり……
萩尾 リンドンは正しそうなことを言ってますけど、あれも間違ってる。というより、リンドンの周辺には、彼のアドバイスがぴったり収まるような事件か何かがあるんでしょう。だけど、どんな正しいことをアドバイスされても、結局、決めるのは本人で、それも本人の頭じゃなくて、皮膚感覚だったり、感情だったりする。
藤本 ええ、ええ。
萩尾 で、よけい困った事態になるとわかっていても、どうしても感情がこっち側に行っちゃうとか。……あ、そっちに質問しようと思っ ていたのにいつの間にか作品を語っている。
藤本 いや、いや、どうぞ(笑)。
萩尾 あのね、創作をしている段階ではね、本当に冷静に話を作っていくと、50ページで終わっちゃうの。だからね、いかにこれを崩すかってことなんですよ。
藤本 えっ、『残酷な神が支配する』は、50ページにまとめようと思えばまとめられるってことですか。本当に?
萩尾 最初にジェルミがね、お母さんの結婚をやめさせればおしまい。
藤本 それはたしかに、そうですけど(笑)。たしかにちょっとずつズレていく話ですよね、あれって。
萩尾 そう。最初にグレッグがきた時に彼を退治して窓から放り出せば、話は終わった。
藤本 凄い(笑)。でも、現実にああいう状況に身を置いてる人っているわけじゃないですか。こっちも読んでるだけでもつらいから、読者もやっぱり救われたくなりますよね。特効薬はなくとも、ベターな道があるんじゃないか、って。
萩尾 でも、「これがベターじゃないか」っていうのをセリフで言っちゃうとね、本当につまんなくなるんですよ。だから、ストーリーを考えてると、読んだ人が「ああ、そうよねえ、そうすればいいのねぇ」って思っちゃいそうなセリフが出てくるんですけど、そういうのは全部、切っちゃうんです。理屈になっちゃうから。
藤本 ああ、そうか。だから萩尾さんの作品って、すごく重層的で、わかりそうでわからない。
萩尾 わかっちゃうとね、やっぱりわかる範疇だけの話になっちゃうんです。説明して終わる、っていうんですか。そうするとね、説明が出てくる後についている有形無形のいろんな感情が、ぜーんぶきれいにこっちに寄せられてしまう。でも、人間ってもっとごちゃごちゃしているものでしょう? だから、そっちのほうを追っかけたいなぁ、と。
藤本 萩尾さん自身も、どうなるかわからないっていう所で描いているって感じ?
萩尾 大丈夫。最後は、できてます(笑)。
藤本 でも、どこかそういう所がないと、作品としての膨らみが出ない、と……
萩尾 いや、作品としての膨らみを出すためじゃない。本来、人間は割り切れないものなんですよ。
同じ傷をなぞるということ
藤本 今回、作品を読み直していて、『残酷な神が支配する』って、実は『トーマの心臓』のユリスモールの置かれた立場を発展させたものだな、って気がしたんです。ユリスモールもサイフリートに「翼をもがれた」って言うわけじゃないですか。それは自分の意思を失って屈服させられたっていうことですよね。ジェルミの体験はそれを発展させたもので、背中の傷も、もがれた羽のイメージとつながってきますよね。それは意識されてるんですか?
萩尾 シンプルな言い方をすると、『トーマの心臓』の場合はユリスモールは聖職者になるんですが、ジェルミのほうは、修道院に逃げなかったキャラクターの話です。
藤本 えっ、ユリスモールが修道院に入ったのは、あれ、逃げたっていう話なんですか?
萩尾 (笑)どうしていいか、わかんなかった。
藤本 なるほど(笑)。ジェルミはそこにとどまって何度も傷をなぞっている。 読んでると、人間は治るために何度も同じ傷をなぞるって言うけど、トラウマって何度も反復されて、なんかそこから逃れることができないのかなあ、って。萩尾さん自身は、ある傷を治すために同じ傷を繰り返しているな、と思うところはありますか。
萩尾 うーん。わかんないけど、何度も同じ話、描いてるなって。藤本さんは、どうですか?
藤本 私は自分で自覚してる最初の傷があって、完璧にそれをなぞってる。たぶん、その時とほとんど同じ状況、同じ条件に身を置いて、「今度は、救われた」っていうのをやりたいんですよ。それでずっと、私の恋愛はうまくいかなかった(笑)。でもさすがにもう、煮え湯を飲まされることにも飽きてきたけど (笑)。
萩尾さんもたしかに同じテーマを繰り返し描かれてますけど、繰り返し描くうちに、最初の原点からだんだん変わってくるとか、以前はこだわっていたことが自分にとって問題ではなくなってくるとか、そういうことって、 ありますか?
萩尾 それはないね(笑)。あんまり。
藤本 ない。そうですか。あの、厳しかったお母さんとの葛藤が一番端的に出たのが『イグアナの娘』だと思うんですけど。
萩尾 そうですね。
藤本 たとえば、「表現してしまえば、その問題は半分解決する」とかってよく言うじゃないですか。だから、ああいう象徴的な形の作品を描いたら、何かかが変わるんじゃないかと思うんですけど(笑)、どうなんでしょう。
萩尾 (笑)。 あぁ、そういう意味だったらね。でも私、一時期、理想的な人間関係っていうのにすごい憧れていたんですよ。理想的な家族関係とか、理想的な友人関係とかね。もしそういうのに巡り合えたら、本当に幸福な時間も人生も持てる、と思っていたんですね。
でもね、それは無理だとわかったの。でね、むしろどんな関係であっても人間関係はいつも混迷で、時々ほんの一瞬、いい事があるだけ。それでいいじゃないか、って。「期待するのはやめよう」。それがわかっただけでもよかったかな、と。
藤本 でも、作品の中では相手をなんとか理解しよう、受け止めようという意識がずうっと続いているように思いますけど、違うんですか。
萩尾 あなたなら、大喧嘩した仲の悪い友達と、相手の環境とか、生き方がわかって、仲直りできる?
藤本 うーん、でも、自分とは違っても、どこか底のほうでつながれる感覚っていうのがでてくるような気がしますけど。
萩尾 状況は変わらない。 状況は変わんないわけ。例えば、相手は、相変わらず身勝手だったり。わがままだったり。だけど、その人がどうしてこうなったかっていう過去のいきさつがわかったとして、さあ、仲直りできるか?
藤本 ちょっと変わるんじゃないですか? 変わらないですか、やっぱり。
萩尾 それは、変わらない。
藤本 言い切ってる(笑)。
「やおい」をどう見るか
藤本 ところで、萩尾さんが『11月のギムナジウム』とか『トーマの心臓』とかを、お描きになった時に、私のまわりでは、すごいセンセーションだったんですよ。「こういうものを待っていた」っていう友達が、すごくいて、特別な印象を残していたんですね。とくに、『11月のギムナジウム』が出た時なんか、そうでしたね。
その後、萩尾さんの作品を皮切りにして、少年を主人公にした物語がたくさん出てきて、今、「やおい」とかあるじゃないですか。それで、萩尾さんなんかは、今の「やおい」の状況をどう御覧になっているのかうかがいたいんです。
このジャンルは「もともとは萩尾さんたちが切り開いた」と言われてるけれど、「やおい」と、あの頃の作品って、全然、違うものだ、って感じがするんですよね。
萩尾「やおい」についてはあまり詳しくはないんだけれど、アシスタントさんにコミケでいくつか買って来てもらったんですよ。
で、読むとね、みなさん優しさに飢えているのね。さりげないことで気持ちを慰めてもらう。
たぶんまんがはねえ、ほんとに感情面が描きやすいジャンルなんですよ。文章で書いたり、詩を書いたりするよりも、キャラクターの顔一つ描いて、目でお互い見合うっていうふうに、それだけでも自分の感情が自ずと出てきやすい媒体なわけ。だから、若い人の間で同人誌がすごく流行るんじゃないかなぁ。
藤本 そうだと思いますよ。なにか感情だけじゃない、無意識みたいなものが……。
萩尾 画面から出てきますからね。学校に行ってね、勉強して、こういう学生になんなさい、こういうこどもになんなさい、っていう用意された安全な世界が目の前にある時に、自分の中で一つ一つぶつかる感情を、どう表現したり処理していいのかわからない。だって、たとえば恋愛一つにしても、マニュアルはないですからね。自分で全部考えてやっていく。なにか、そういった感覚の部分が、「やおい」のほうに流れている。それで、若い人に支持されているんじゃないかなと思う。そういうのが、私の「やおい」観。
藤本 なるほど。それから、もう何度も聞かれていると思うのですけども、萩尾さんが、ああいう『11月のギムナジウム』のような少年を主人公とした作品を描こうとしたきっかけというか、動機というかを「やおい」観との比較において語っていただけると……
萩尾 うーん。藤本さんの場合はどうなんですか?
藤本 私の中には、あまり主人公が少年でなきゃいけないというのはないんです。むしろ、 自分っていうものをきちっと持った女の子、っていうのが主人公としては一番好きかな。たとえば『スター・レッド』の星とか。でも、ある時期から先、とくにこの頃の萩尾さんの作品の中に出てくる女の子って、サンドラもそうだしナディアもそうなんだけど、なんか泣くばっかりですよね(笑)。
萩尾 うーん。
藤本 ああいうのは、私は嫌なんですよ。でも、男の子だけがよい部分を持ってるということでもないだろう、っていう感じもあって。私自身、「女であることの重力につかまりたくない」という部分はあるんだけど、逆に女という性を楽しんでいる部分もある。だから、「やおい」にはまってる子たちのように「少年じゃなきゃいけない」っていうのが、実感としてあんまりない。「男で遊ぼう」って感じもあんまりないし。で、萩尾さんは?(笑)
萩尾 私は『11月のギムナジウム』を描いてる時、面白かったんですよ。プロットを作る時に、一応、少女まんがなんだしと思って、女学校の話も作ってみたんです。男子学校バージョンと一緒に。そしたらね、女学校バージョンは、ネチネチしてるんですね。
藤本 ええ。
萩尾 だから、これは男子学校バージョンのほうが面白いと思って。そっちにしたらね、なんか、描いててホクホクしちゃうんですよ。知らない世界だから(笑)。想像力が刺激されるというか。それで、自分でも、描いてて面白いのではまっていったところもありました。で、描きながら思ったのは、あぁ、「女の子はこうしなきゃダメだ」という魔法使いの呪文がね、自分を縛っているんだなぁって。
だからどうしてもね、女性キャラクターを描く時に、なんかねえ、躊躇するんです、色々と。 男のキャラクターのほうがラク(笑)。
藤本 あぁ、そうか。 読者にシンクロしなきゃいけないから。
萩尾 読者というよりはね、ついつい男の人に好かれるキャラクターを描こうとしちゃうんです。こういう名前の女の人は、男の人は嫌いだよね、とか。急ブレーキがかかる。あと、男の子のほうが描いててなんか、解放感が違う。
藤本『X+Y』とか『11人いる!』のフロルとか、両性体で男と女どちらにも変化できる存在をお描きになるのも、やはり同じ動機ですか?
萩尾 そうですね。決まった性がない時、 識は転換する、というのを描きたかったんです。その時、周囲はどう対応するか。『X+Y』の場合は、ちょっと変わったキャラクターにしちゃいましたからね。
進化・世界・双子
藤本 特異な存在って、やっぱり、あんまり性的じゃないんですね。そういう意味では、『ポーの一族』のエドガーもそうだと思うんですけど。あるいは、『銀の三角』とかっていうのもそうですよね。
で、そういったものが時空を越えて続いて行くんだけれども、それがその後、進化の袋小路に入っているみたいなモチーフが、とくにここ十年くらいよく出てきますよね。この世界はすでに終わってしまっていて、「世界は終わってしまったものが見ている夢だ」っていうイメージが、何度も何度も形を変えて顔を出す。失われてしまった世界の影。あるいは進化を夢見るイグアナ。『スター・レッド』の中で必ずしも超能力が「進化」じゃなくて「退化」の一種として捉えられているのも印象的でしたし。
萩尾望都の中で、世界は進化しているのか、退化しているのか。萩尾さんの中では人類は進化の袋小路に入っているという感覚があるんですか?
萩尾 それはよくわかりませんねえ。私は一つ何かわかると、それに対して、そうかなあ、本当かなあ、っていつも考えちゃうんですよ。
たとえば人間は進化してると言われるけど、ほんとにそうなのかな? 理由は何? 言葉が使えるとか、宗教ができたとか、都市を作ったとか、道具を作ったとか、その他には? それはほんとうに進化なの? とかつい考えちゃうんです。
藤本 なるほどね。ところで、萩尾さんは何度も双子について描いてらっしゃいますよね。そして、たしか『MOE』の双子についてのインタビューで、「人が大人になるためには、親殺し、子殺し、そして自分殺しをしなければならない」みたいなことをおっしゃってる。
実際、萩尾さんが双子を描かれる時、全き〈対〉、自分の分身みたいな感じであらわれてくる時と、片方が片方を殺す、みたいな形であらわれてくる時とあるんですけど、それを萩尾さんご自身は、どういうふうに位置づけていらっしゃいますか。
萩尾 双子というのは要するに、鏡にうつった自分、というふうに考えると、その自分が愛しい時と、消し去りたい時と、そのバリエーションのいろんなバージョンを描いてるっていう感じなんですよ。スペアがあるとねぇ、よく見えるんですよ、相手が。だから、自分をうつす鏡としての双子なんですよ。理屈で言えばね。
藤本 それは、今の私ではない本当の私がどこかにあるはずだとか、そういうのではないわけですよね。
萩尾 いや、そうじゃないですね。
藤本 先ほどの世界観にもつながるんですけれど、萩尾さんの世界では窓が象徴的で、「窓の向こうに、私の本当に住んでいる世界があるような気がする」と何かでおっしゃっていたことがありましたよね。その感覚とも共通性がありますか?
萩尾 それとは、全然、違います。つまり、双子の相手っていうのはね、本当に、等身の自分なんです。指導者でもないし、年下の誰かでもない。自分には見えない、自分のある部分なんですね。
藤本 最後にもう一つ。萩尾さんの作品の中には、少年が空を飛ぶとか、少年の背中にある翼、というようなモチーフがよく出てきますね。 私、野火ノビタさんの「やおい」作品である『飛行少年ズ』を読んでいて、あっ、「やおい」の原点にあるのはピーターパンなんだ、って突然思ったんです。あれも家庭から飛び出していった少年の話なんですけど、少女まんがの原点って、色々考えて行くと、家庭の中で生まれた傷みたいなものにあるような気がして。で、そのもとになる近代家族が生まれたのも、この二百年くらいのことで。『ピーターパン』だけでなく『赤毛のアン』だって「メアリーポピンズ』だってそういう背景があってはじめて生まれてくる。そういうファンタジーと、「飛ぶ少年」っていうのが、なんか重なって、つながってくるんじゃないか。
萩尾 それは、面白いですねえ。二百年の家庭の歴史っていうの?「バルザックから小説が始まった」とか言いますし、やっぱり近代都市が人間関係とか、そういうのを作り上げて行く、それの延長線上にあるかもしれないですね。
藤本 ええ。おそらく、それを一番先端的な形でとらえているのが少女まんがで、なかでも萩尾さんの作品じゃないかと思ってるんです。
萩尾 今日は私からもいろいろ聞くつもりだったのに、やっぱりプロのインタビュアーに負けたという感じで(笑)。やっぱり、色々、質問されてしまった。
藤本 いえいえ、今日はどうもありがとうご ざいました。
「少女まんが魂(188-206ページ)」のインタビュー
「少女まんが魂」現在を映す少女まんが完全ガイド&インタビュー集
著者:藤本由香里
発行日:2000年12月20日
出版社:白泉社
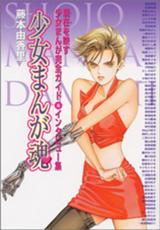
ロングインタビュー
萩尾望都
(図版に続いてテキスト抽出あり)










ロングインタビュー
萩尾望都
どんな関係であっても、人間関係はいつも混迷で、時々ほんの一瞬、いい事があるだけ。それでいいじゃないか、って
逆インタビューではじまる
藤本 今日は、なにか、萩尾さんのほうからも私に質問があるという(笑)。
萩尾 ええ、まんが家は質問されるばっかりだから、たまには質問してみたいなっていうのと、藤本さんのまんがの評論を読んでいると、藤本さんっていう人が、非常に面白いなあと思って。
藤本 あッ、ありがとうございます。とても光栄な事なので、じゃあ、まず攻守を逆にして、萩尾さんのほうから……
萩尾 はい。じゃあ、いいですか? 私がいつも聞かれるのは、「いつ頃からまんがを描き始めたか」とか「読み始めたか」とか。なんかパターンなんですけど、それからお聞きしていいですか?
藤本 はい。私はあんまり絵が上手じゃないので、「まんが家になろう」と思ったことはないんですが、読み始めたのは、手塚治虫さんの『リボンの騎士』が最初なんです。
父親の散髪についていったのがきっかけで、父親が散髪している間に、なんかそこの床屋さんに『なかよし』が三冊ぐらいあったんですよ。それで、読み始めたらもう止められなくなって、夢中になって読んでて。
でも、男の人の散髪って、すぐ終わるじゃないですか。だから、父親が「帰ろう」って言ってるんですけれども、とにかく「ちょっと待って、ちょっと待って」。そしたら床屋のおじさんが、「いいよ、それ、おじょうちゃん持って帰って」。もう天にも昇る心地でしたね。それが一番最初です。
それから「まんがって面白いものだな」と思って、なんか近くに貸本屋さんがあったもので、そこにとにかく通って。
萩尾 貸本屋さんで借りたのは、当時の「赤本」っていう単行本なんですか? それとも 普通の雑誌?
藤本 単行本と雑誌と両方、借りてました。ただ、あんまり借りてくるもんで、母から禁止令が出て、「月曜日に一冊だけ借りていい」っていうふうに決まったんですね。だから、読めるのは月に四、五冊。
萩尾 月曜日に一回、一冊だけ?
藤本 ええ。あと、かわいがってくれていた大叔母が、『なかよし』は買ってくれてたんです。で、その頃、貸本屋で借りてくるまんがはほとんど少年誌を読んでました。
萩尾 えッ、ちょっと待って。『なかよし』の次に少年まんが誌を読んでた?
藤本 はい。ちょっと変なんですけど、考えてみると、やっぱり手塚さんに惹かれてたんだと思うんです。その頃、『少年』とか『ぼくら』とか『少年画報』『少年ブック』とかあって、そこに『ふしぎな少年』とか、『鉄腕アトム』とかが連載されてたんですよ。たしか少し後に『ビッグX』とか。ちょっと年代はわからないんですけれども。
だから、そういった少年月刊誌をだいたい借りてて。あと、たまに『りぼん』を読んでいましたね。やっぱり、なんか『りぼん』のほうが、ちょっとお姉さんらしい感じが、その当時あって。
萩尾 はい。そうですね。
藤本 だからむしろ、『りぼん』を毎回読むっていうよりは、『ぼくら』とか『少年』を読むほうが当時は面白かった。で、あとは今村洋子さんとかの単行本を借りてました。
それからほら、叔母の家に行ったり、祖母の家に行った時っていうのは、「何か買ってあげようとか」とか言われるじゃないですか。 そういう時、貸本屋さんでまんがを借りたい、っていうのがその頃の一番の願いだったので、遊びに行くたんびに、そこの近くの貸本屋さんで何冊か借りていた。そういうことの積み重ねで今まできました。
萩尾 えっ、一人っ子ですか?
藤本 いえ。四人兄弟です。 萩尾さんと同じですよ。 私は一番上ですけど。
萩尾 あッ、長女なんですか。じゃあ、お姉さんが一冊借りて読むと、下の兄弟がそれを読む。
藤本 ええ。そうですね。
萩尾 あの、妹さんもいる? それともご兄弟ばっかり?
藤本 いや、すぐ下は弟で、あと妹、弟ですから、女、男、女、男っていう順序なんです。だから、下の子たちはほとんど少女まんがを読んで育った。私が少年まんがを読んでいた頃っていうのは、まだ下の子が生まれていなかったり、小さかったりしましたから。
萩尾 ああ。じゃあ、小学校の低学年の頃ですね。それだと。
藤本 そうですね。最初に読んだのが五歳ぐらいですから。それから小学校四、五年くらいまで、男の子のまんがを読んでました。でも、あの頃、少年月刊誌って次々に休刊になっていきましたよね。
萩尾 そうですね。うん、うん、うん。
藤本 それで、私も十歳くらいになってくると、だんだんなんか女の子のまんがのほうが面白くなってきて。で、それからは、別冊マーガレット』とか、『りぼん』とかも読み始めて。『なかよし』はずっと続けていたんですけれども。それから「週刊マーガレット』とか、別冊少女コミック』とか、『週刊少女コミック』とか、そちらのほうに行ったんです。
萩尾 ああ、本当に大量のまんがにうもれて育ってきたんですね(笑)。
藤本 その通り(笑)。だから、下の子たちに、少女まんがの影響がすごく強くって。うちの弟のところに女の子が二人いるんですけど、その名前が「さくら」と「更紗」っていうんですよ(笑)。
萩尾 凄い。
藤本 私はその名前を聞いた時に、いやー、これは私が思っていた以上に少女まんがを読ませた影響は大きいかもしれないって(笑)。
萩尾 弟さんがつけられたんですか?
藤本 そうなんです。
萩尾 えー、本当? でも、更紗っていう主人公のまんがってありましたっけ。さくらはよく聞いたけど。
藤本 ええ、田村由美さんの『BASARA』の主人公が更紗です。ちょうど連載が始まった前後かなぁ、更紗が生まれたのは。もしかしたらそれよりはちょっと前かもしれないけど……でも、そういう特定のものからとったっていうよりはーー
萩尾 イメージ。うん、なんか。
藤本 そう。イメージがやはり、少女まんが的感性なんじゃないかなと思うんですよね。
藤本、「家庭内文化大革命」 を体験する
萩尾 そうなんですか。あの、私ねぇ、藤本さんの評論を読むとね、なんかこう「すごく優等生で、頭のよい人だなぁ」っていう印象が強いんですけど。
藤本 そうですかぁ。
萩尾 あんまり、親に心配掛けないタイプっていうか。
藤本 いや、優等生って、そういう意味だとすると、ちょっと違うかもしれない。たしかに学校の成績とかはよかったんですけど、いわゆる「優等生」っていう言葉で括られるようなよい子だったっていう感じは、自分ではしないんですね。 私の自己認識では、かなり内気な子で、わりと「萩尾さんもそうだとうかがってますが、まわりから「変わってる、変わってる」って(笑)言われるこどもでしたね。
どっちかっていうと、「夢見がちな少女」っていうようなところが多かったんじゃないか なぁ、という気はします。
それからなんというか、ちょっと成績がよかったりしたことで、もう、すごい違和感があるっていうか、それで周りの不興をかったり、ちょっと意地悪されたことが、小学校の五年生くらいからあって。
萩尾 なんか、この頃のいじめって、成績のよい子がいじめられるんですって。その類いなんですか?
藤本 そこらへんになると微妙なんですけど、自分でもすごい罪悪感があって。それに、親も成績がいいっていうことを評価しない。むしろマイナス。
萩尾 うーん、えぇ? そうなんですか?
藤本 ええ。とくに父親から、なんか「人間的に欠陥がある」みたいなことをけっこう言われて……。
萩尾 ふーん、それは、ちっちゃい頃から?
藤本 ちっちゃい頃から。
萩尾『なかよし』、もらってきたから?
藤本『なかよし』(笑)、もらってきたからじゃないんですけど、簡単に言うと、うちの父親って社会主義者なんですよね。共産党員じゃないんだけど、学生時代に大学の学生運動の書記長かなんかやってて。
萩尾 あぁ、すごい。なんとなく……うーん、はい、真面目な人なんだ。
藤本 ええ。それで、運動系の言葉に、「自己批判せよ」っていうのがあるでしょ。
萩尾 ありますねぇ。
藤本 あれをこどもに対してやるんです。なにかというとそんな感じで本気で批判される。まだこどもなのに(笑)。しかも不幸なことに私が、自分が何を言われているのか理解できるこどもだった(笑)。
あとで考えてみればちょうどその頃、日本共産党の査問があったり、中国の文化大革命が起こったりしてた時で、私は今になってそれを「家庭内文化大革命」って呼んでいるんですけれども。『イワンの馬鹿』とか読まされて、お前は民衆の敵だって。
萩尾 そんなー。でも、お母さん、かばってくれませんでした?
藤本 いやぁ、かばってくれませんでしたね。
萩尾 お母さんも、自己批判してたのかしら。
藤本 (笑) うん。母は母で、ちょっと違う感じで激しい人だったんで。
四人こどもがいますでしょう。でもずっと働いていたんですよ。学校の先生だったんですけど。
萩尾 あぁ、学校の先生……。
藤本 ええ。で、忙しかったせいもあるんでしょうけど、なにかというと怒鳴られるとか、手が飛んでくるとか。
萩尾 学校でもそうだったの? お母さん?
藤本 学校では、そんなにぶったりしてないと思うんですけど。でも、あの、校内暴力がすごくなってた時、ありましたよね。あの頃、母は実業高校の先生だったんですけど、授業をしている時に、三年生の男の子の一人があんまりうるさいんで、「出て行きなさい」って言ったらしいんですよ。するとその子がすぐ出ていった。そしたら、「なんで出て行けって言われてすぐ教室を出ていくのか」って言って、高校三年の男の子に平手打ちをくらわしたらしいんです(笑)。
萩尾 うそー(笑)。
編集者 強い(笑)。
藤本 私もさすがにそれを聞いてびっくりして、こどもの頃、自分がけっこうビシビシやられて育ったのも、「こういう人だったらしょうがないかな」みたいな感じを持ちましたけどね。
萩尾 豪傑。豪傑っていうか、凄いねぇ。うん。
藤本 ただ、当時はやっぱりそういうふうに怒鳴られたりするのは嫌だった。落ち着かないし。
父のことにしても、そういう家族体験っていうのは、相当トラウマになっているなと、自分でも思う。
萩尾 いや、でも、お母さん、学校の先生していて、一日中、生徒を相手に授業をしてきて、家に帰って四人こどもがいるって、それはヒステリーも起こすかもねぇ。でも、こどもは大変ですね。
藤本 ええ、こどもは大変ですよ。大きくなってからは、ああ、父親は別に家事する人じゃなかったし、母も余裕がなかったんだろうなあ、とわかるんですけどね。だけどやはりこどもにしてはかなり厳しい体験だったし、そうすると、「自分は本当にこの世に存在していてもいいのだろうか」って、思い始めるわけですよ。その頃のそういう気持ちに、そのころ萩尾さんのお描きになっていた少女まんがが、こう、すーっと入ってくるっていうのか、すごく救われたという気がしました。
萩尾 そうかぁ。私、藤本さんの『私の居場所はどこにあるの?』っていう評論を拝見して、お会いすると美人だし、頭もいいのに、でもずいぶん何か迷いっていうか不安感があるんだなあ、って。今うかがってて、そういう女の人って多いのかなあ、って思っちゃいました。
異端の存在を描くということ
藤本 ええ。でも、萩尾さんご自身はどうなんでしょう? 四人兄弟の二番目でいらっしゃるんですよね。
萩尾 そうですね。まぁ、うち、だんご四兄弟(笑)だったんですけど、上と下がちょっとおっとりしていて、真ん中の二人が、ちょっと性格がきついっていうか。挟まれるとそうなっちゃうかなっていう、自分でもその諦めがあるんですけれど。
藤本 えーと、一番下が弟さんで、上三人が女の子でしたよね。仲のよいご兄弟だったんですか?
萩尾 いや。すごい仲悪かったんですよ。でも中学校の頃、まんがなんか読んでいてもわりとみんなアットホームでしょう? 今村洋子さんのまんがとか。だから、こんなに仲の悪い兄弟なんて世界中でうちだけだろうなとか思ってましたよ。でも、成人して各自家を出ていったら、なんとなく仲よくなりましたけど。
藤本 それぞれ幾つくらい違うんですか?
萩尾 二歳、二歳、二歳、えーと、最後は四歳か。
藤本 私のところは、二、三、三、なので、だいたい同じようなものですね。一番上のお姉さんが、たしか小夜さんとおっしゃるんですよね。『小夜の縫うゆかた』っていうのは、お姉さんがモデルなんですか?
萩尾 いや、名前だけ借りたんですよ。
藤本 そうですか。……萩尾さんの作品っていうのは、母殺しの作品が多いっていわれてますよね。初期作品もだけれど、最近の作品でも、『メッシュ』とか『残酷な神が支配する』とか。どこかで萩尾さんのお母様もうちと同じく厳しかったっていうようなこともお書きになってますよね。
でも、萩尾さんの作品を拝見していると、やっぱり、「うちの親子関係とは違うな」って感じがするんですけど。
萩尾 うーん。「自分は存在していていいんだろうか」っていう問いはね、それこそ、私も中学校のころずっと悩んでいたんですけれど、心理学者なんかにいわせると、それは、物を考える人が思春期に必ず通る成長過程の一つのパターンだっていうんですね。
中学校の頃は、まわりに誰も相談する人はいなかったけれど、成長して他の人に話してみると、「いやぁ、私もそうだった」っていわれる。やっぱり成長して自我を確立していくっていうのは大変なことなんだなあ、と思いますね。
『ポーの一族』を描いた時にも、主人公は吸血鬼だったんだけど、あれは要するに、世の中の生態のルールから全く外れたものが存在している時に、では私たちはどうやって自分たちの存在を確認するのかというので、あのキャラクターを設定したんです。するとけっこう、共感してくれる読者がいる。あの時は、「どこが受けたんだろう」じゃないけど、不思議は不思議だったんですね。でもお話をうかがってると、やっぱり皆、存在の不安みたいなものを抱えているのかな。
藤本 ええ。でも、萩尾さんが「変わってる」と言われていたとか、あるいは、異端のものを描こうとする、その異端の感覚っていうのは具体的にはどんな感じなんですか?
萩尾氏マネージャー 私、一つ例、いっていい?
藤本 ええ。どうぞ。
マネージャー たとえば、クラスメートがタレントの話をしてるとしますね、今だったら、ジャニーズ系とか。すると萩尾さんはそれに興味がないから、それで話が盛り上がっている時に「それよりさぁ、SF読んだ」って答えるの。
藤本 (笑)。
萩尾 と言って、嫌われていた人(笑)。
藤本 でも、そこで「SF読んだ?」って割って入れるっていうところが、やっぱ、萩尾さんの健康さって言うか、強さだと思うんですよ。聞いているとなんか、私もたぶん似たような位置どりだったと思うんですけど。つまり、アイドルの話とか、あるいはテレビの話とかで、皆が盛り上がっているのに、なんか違和感がある。うまくそのリズムに入っていけないんですね。たぶん何かリズムが違うんです。ものを考える時の。
萩尾 そうですねぇ、リズムねぇ、うん。
マネージャー だから、昔はねぇ、私が「開放的自閉症」って言ってたわけ。
萩尾 あぁ、そうそう「明るい自閉症」って(笑)。なんで、自閉症っていうのかって言うと、これは、まあ、ギャグで使っているんですけど、要するに対人コミュニケーションにズレがあるっていうんで。
藤本 その時に萩尾さんのその明るさって、どこからくるのかな。私なんか、「自分が悪いんじゃないか」と思っちゃうんですね。「家庭内文化大革命」を経てきたからかもしれないけど。
マネージャー 私、思うんですけど、藤本さんは意外と他の人のこと考えているじゃないですか、ちっちゃい時から。でも、萩尾さん系統の人は、他の人の事情や都合をうまく考えられないんですよ。自分で精一杯だから。
藤本 (笑)。
マネージャー 萩尾さんは自分のことをまんがに描いて、それに共感する人が「先生なら私のこと、わかってくれますよね」ってファンレターをくれるけど、でも、どちらも魂の孤独はあるんですけど、じつは自分のことで精一杯。それが共感をよぶシステムなんですよ。萩尾望都の。
藤本 でも、なんか萩尾さんは基本的な所では、やっぱり支えられているというか、実は、かなりいいご両親だったんじゃないかなっていう気はするんですけど。そんな事はない?
萩尾 いや、あなたの話を聞いてると、うちはよかったんだなぁと思う(笑)。
藤本 (笑)。そうですねえ。たとえば最近、よく「アダルトチルドレン」って言葉を聞きますけど、萩尾さんなんかは、自分はアダルトチルドレンだって思いますか?
萩尾 うーんとねぇ。思います。
藤本 えっ? 思います?
萩尾 はい。 思いますね。
藤本 どういうところで? 私、「思わない」っておっしゃると思ってたんですけど。
萩尾 いやぁ、私、橘由子さんの『アダルトチルドレンマザー』っていう本、面白かったんです。お母さんがあまりにも立派で管理的なために、どんどんこどもが自信をなくしていくっていう。ああいう感じは非常によくわかるし。つまり、親が決めた「あなたはこんなふうにやりなさい」っていう規範に従えないでいる自分をやっぱり責めるわけですよ、悪い子だって。そういう状態が、三十歳まで続いているから。
三十歳の時の大ゲンカ
藤本 というと、三十歳の時に、何か転換があった?
萩尾 大喧嘩があって。
藤本 (笑)。たしかまんが家になる時も反対されたんですよね。それは、お父様の反対だったんですか? お母様は、金賞をとったらあんまり何も言わなくなったと書いてらっしゃいましたけど。
萩尾 母のほうは、まあ、勉強の邪魔になるっていうので反対でした。それから、やっぱりまんがっていうジャンルがわからないもんですから、「変なことをしてる」と思って拒否してたんです。で、父親のほうは、要するに、「そのうち止むだろう」と思ってるわけです。ですから、金賞もとって、お金をもらったことで、とりあえず家でまんがを描くっていうことは許してもらったんですね。ところが、やっと上京してまんが家になることになって、着々とプロの道を歩んでましたら、三十歳近くになって、「そろそろ止めたら」っていう話になって(笑)。
マネージャー 昔の人だから、価値観が「女性は、結婚して一人前」。それから、萩尾さんは当事者だからわかんないと思うんですけ ど、はたから見ると、この人のお父さん、非常にユニークな人ですよ。
萩尾 (笑)。
マネージャー この変さは、お父さん譲りです。萩尾さんのお父さんはですね、本当に珍しい人です。一種の天才気質なんだと思うんですけどね、村では生きにくい。
萩尾 (笑)。父親も、あの、対人対応力っていうの、ちょっと欠けてまして。そのぶん、何か、ちょっとすっとんだような人なんですね。
藤本 えっ、どういうふうに?
萩尾 なんか、あのー、過剰に他人に対して親切にしようとする。本人に悪気はまったくなくて、周辺の悪意も信じない人なんですけど、やっぱりTPOが悪くて、迷惑する時もありますよね。そう言うと、こちらが好意でやっているんだから、向うが喜ぶのが当然であって、それが迷惑だっていうのは、その人がおかしいんじゃないかって言うんです。
藤本 それはあの、『感謝知らずの男』で、 凄い親切な隣人(笑)っていうのが出てきますけど、あれって、なんか、反映されていますか。
萩尾 はい。あれは父を観察したモデルです(笑)。
藤本 でも、ある時期までは理想のお父さんだったんでしょう?
萩尾 そうですね。うちは、母親がきついぶん、父親は、非常に優しい人でした。
藤本 それで、三十歳の時の大喧嘩っていうのは?
萩尾 あの頃は、ちょうど父が退職した頃で、私のほうは単行本が毎月出始めた頃だったものですから、税金の申告なんかが大変になってしまって、それで、会社組織にして父に会計をやってくれないかって頼んだんですよ。でも、まんが家の仕事場ってのがよくわかっていなくて、私が一種、お絵描き教室をやってると思っている。だから、アシスタントさんが来て、手伝ってもらってお給料渡しますね、そうしたら、「なぜ、お弟子さんにお金を渡すの? 普通はね、お弟子さんが先生に持ってくるんだよ」って。
藤本 なるほど。
萩尾 そういうのから始まって、本当に一事が万事、ズレていくんです。説明すると「ああ、わかったよ」って言うんだけど、また翌月、払う段になると同じことを言う。
藤本 (笑)。はい。
萩尾 で、当時は、ちょっと狭い家に住んでいたもんですから、仕事中に父が上京してきても寝る場所がない。とくに締切りが重なっちゃいますと、「ホテルに泊まって」というわけです。すると父は、それは嫌だ、「わざわざ上京して娘のところにきたのに、なんで親が旅館に行かなきゃいけないんだ。アシスタントさんたちをそっちに泊まらせなさい」。そんなことはできないというと、お父さんがくる間は仕事休みなさいって。
藤本 マイペースなんですね、とにかく。
萩尾 まあ、そうですね。そして帰ってから母に、娘の家にいったら旅館に泊まらされたとか、仕事でろくに話ができなかったとかっていうわけです。すると母が怒って「仕事なんか止めてしまえ」。それでどんどんこじれていったんですね。
藤本 はい。それで結局、最後の爆発が起こったと。
萩尾 ええ。「もう、私は会社を潰します」って言って。
藤本 それでどうしたんですか?
萩尾 社長は父だったんです。だから私はクビになりました。
藤本 (笑)。それはかなり尾を引いたんですか?
萩尾 ええ。その後、三年くらい口をききませんでしたね。
「まんが家をやめて童話作家になりなさい」
藤本 その大喧嘩がちょうど三十歳ぐらいだというと、ご両親には、もうそろそろ仕事を止めて結婚しなさい、っていうのがすごくあったんですか?
萩尾 それもあったみたいですね。母も、父も。要するに、もうお金もできたし、名前も知れたし、そろそろまんが家をやめたらどうかと。とくに母は、まんがっていうものがまったくわからないし、好きじゃないから、「お母さん、親戚の人に娘がまんが家ですっていうのは恥ずかしいから、童話作家になんなさい。童話作家だったらいいから」って(笑)。
藤本 それもすごい(笑)。
萩尾 趣味で描いてればいいんじゃないのって。
藤本 いや、なるほどね。でも、その頃っていったらもう、『ポーの一族』とか、『トーマ の心臓』とか出てて、萩尾さん、ものすごく有名になってますよね。
萩尾 でも両親は、出版界とは関係のないところで生活していますから。
だから私が「いや、まんがやめたら、いったいどうやって食っていけっていうの?」と言ったら、「テレビとか新聞に出ればいいじゃないか」(笑)という恐ろしい答えが返ってくるという。うーん。「もう、こういう人とは話したくない」って。
藤本 でも、萩尾さんはまんが界だけで有名だったわけじゃなくて、それこそ新聞とか、そういうメディアでもとり上げられてましたよね。それを見て、「立派な仕事してるんだ娘は」っていうふうにはならない?
萩尾 実は私も、母がまんがを嫌いだったけれど、ああいうメディアに出てれば、そんなふうに考えてくれるかな、と思ってたんですよ。だから依頼が来ると、仕事の合間にちょっと出てたりしたんですけど、結局、まったく理解には遠かったんだっていうことがよくわかりました。
マネージャー 結局、描いてるまんががもとで有名になったと思ってなかったんですね。
藤本 ああ、そうか。お父さんやお母さんにとっては、逆に、テレビに出たり新聞に出たりするから有名なんだ。だったら人聞きの悪いまんが家(笑)なんかやめて、そっちで食べていきなさい、と。
こどもの混沌状態を描くのが面白い
藤本 私は、萩尾さんの作品は『なかよし』にお描きになったデビュー作、『ルルとミミ』から、ずっとすごい好きで、『ケーキケー キ ケーキ』とか。あれ、別冊付録でしたよね、私の記憶では。
萩尾 そうですね。はい。
藤本 でも、その後、『少女コミック』のほうに移って、ぜんぜん作風が変わった。でも逆に、その頃から萩尾さんの魅力がどーっと開花したっていう感じがして。
『ポーの一族』や『トーマの心臓』ももちろんだけれども、当時、『塔のある家』とか 『キャベツ畑の遺産相続人』とか大好きだったんです。あのへんの作品は、なんていうのかな、「こどもの頃生きていた空気」みたいなものとすごく結びついていて、読むとその頃の感情っていうのがどーっと蘇ってくる感じがするんですよね。
萩尾 こどもの感覚、こどもの考えていることっていうのには興味がありますね。やっぱりこども時代の一日一日っていうのは、毎日毎日、発見につぐ発見の連続ドラマなんですよ。これまで知らなかったことを知って、また知って。前に知ってたことと次に知ったことが結びついて、っていうぐあいに、非常に目まぐるしく変わっていく。けれど同時に、そんなふうにして知る世界は断片的だし、力もないし、いろんなことを考えるんだけど、どこに向かってそういうものを話せばよいのか、形にしていけばよいのか、わからないでいる。その混沌状態がすごく面白い。
藤本 ほんとに混沌状態ですよね。
萩尾 で、選んだジャンルが少女まんがだったせいもあって、ちょうどその時代を思い出しながら描くのがね、けっこう快感なんですよ。
『残酷な神が支配する』と人間の混沌
藤本 萩尾さんは、デビューなさってからもう三十年くらいになりますよね。そうすると、萩尾さんのこども時代と今のこどもとはずいぶん変わってると思うんです。それで、萩尾さんの場合は、自分のこども時代に常に帰っていって、それを作品を描く原動力にしているのか、あるいは、もうちょっと今の時代を生きるこどもと意識をシンクロさせていくことで作品が生まれてくるのか、そのへんをうかがいたいんですが。
というのは、今お描きになっている『残酷な神が支配する」。この作品は、今まで萩尾さんが描かれてきた親子の問題とはまた、何か一つ違うところにいってますよね。 始まったのがちょうど、ささやななえさんの『凍りついた瞳』など、社会的にもチャイルドアビ ューズ(こどもへの性的虐待)への関心が高まってきた頃ですけど、そういうことと関係があるのかどうか。それからこの作品では、こんなハードな体験、っていうか、息苦しくて、なにもここまで……っていうような世界にまで入ってきますよね。萩尾さんがどうしてこういうテーマをお選びになったのか。
萩尾 あのテーマを選んだいきさつは色々あるけれど、描きながらけっこう自分でこだわっている部分っていうのは、自分が過去に失敗した人間関係です。
直接的な話じゃないですよ。でも、それを形を変えてずいぶん入れてるっていうのがあります。こんなふうにすると失敗するとか(笑)。
藤本 たとえば?
萩尾 うーん、三十歳で親子喧嘩した話とか(笑)。人に何かを話してわかってもらう、自分の気持ちを伝えるってことって、本当にむずかしいなっていう.……
藤本 なるほど。具体的に作品にそくして言うと、たとえばイアンの行動。萩尾さんはどこかで「イアンの行動っていうのは間違っている、だから皆さん、ああいう真似をしないように」っておっしゃってましたよね。端的にいって、イアンの行動はどこが間違っているんでしょう?
萩尾 なんかね、その話をすると、舞台裏になって、また話も長くなっちゃうんですけど。人間ってね、あのー、またうちの父の例を出してすいませんが(笑)。
藤本 (笑)。はい。今日はお父さんシリーズ。
萩尾 たとえば、自分がよいと思ってやったことなら皆が感謝するはずだ、というあの間違ったセリフ。そういうものがあったりするわけですよ。だからたとえば、イアンがジェルミを迎えに行って、引き戻して更生させようとしてますが、あれは余計なことです。言ってしまえば。
藤本 でも、普通に考えて、ジェルミが男娼になってクスリまでやってるという状態をみると、やっぱりなんか、手を出したくなるじゃないですか。 私だって手を出したくなると思う。
萩尾 うん。そう、そう。だから、あれはね、手を出したくなった人が不幸になるというパターンを描いているの。
描き手の私としては、イアンが正しい事をしてるって意味で描いてるわけじゃない。この人の性格だったら、こんな事するだろうと思ってやってる。でも、読者によっては、そこを一緒にしちゃうわけですよ。だから、その時に、「あのう、皆さん、イアンが正しい事をしてるとか、思わないようにしましょう」って、その人のために言ったんです。
藤本 あぁ、そうか。ではどうするのが正しいんでしょうか?
萩尾 それがねぇ、正しい道っていうのはないんですよ。人間関係においてはね、まずくてもやらざるを得なかったりね。でも、そうやってるなかで別の解決法が見つかったりすることもあるんですけどね。
藤本 主人公のジェルミは、いろんな傷をもう一度繰り返しながら行きつ戻りつしてますよね。あれを見てると、やっぱりあれだけの体験を乗り越えるのには時間が掛かるんだな、というのはすごく伝わってくるんです。
だけど一方で、リンドンがイアンに、ジェルミがどんな状態になっても「そのまま落としておきなさい。手を出すな」って言うじゃないですか。で、「あなたは何度も彼を裏切っているんだから、彼があなたを信じると思うのか」みたいなことを言う。それは正しいんだけど、でも、やっぱり……
萩尾 リンドンは正しそうなことを言ってますけど、あれも間違ってる。というより、リンドンの周辺には、彼のアドバイスがぴったり収まるような事件か何かがあるんでしょう。だけど、どんな正しいことをアドバイスされても、結局、決めるのは本人で、それも本人の頭じゃなくて、皮膚感覚だったり、感情だったりする。
藤本 ええ、ええ。
萩尾 で、よけい困った事態になるとわかっていても、どうしても感情がこっち側に行っちゃうとか。……あ、そっちに質問しようと思っ ていたのにいつの間にか作品を語っている。
藤本 いや、いや、どうぞ(笑)。
萩尾 あのね、創作をしている段階ではね、本当に冷静に話を作っていくと、50ページで終わっちゃうの。だからね、いかにこれを崩すかってことなんですよ。
藤本 えっ、『残酷な神が支配する』は、50ページにまとめようと思えばまとめられるってことですか。本当に?
萩尾 最初にジェルミがね、お母さんの結婚をやめさせればおしまい。
藤本 それはたしかに、そうですけど(笑)。たしかにちょっとずつズレていく話ですよね、あれって。
萩尾 そう。最初にグレッグがきた時に彼を退治して窓から放り出せば、話は終わった。
藤本 凄い(笑)。でも、現実にああいう状況に身を置いてる人っているわけじゃないですか。こっちも読んでるだけでもつらいから、読者もやっぱり救われたくなりますよね。特効薬はなくとも、ベターな道があるんじゃないか、って。
萩尾 でも、「これがベターじゃないか」っていうのをセリフで言っちゃうとね、本当につまんなくなるんですよ。だから、ストーリーを考えてると、読んだ人が「ああ、そうよねえ、そうすればいいのねぇ」って思っちゃいそうなセリフが出てくるんですけど、そういうのは全部、切っちゃうんです。理屈になっちゃうから。
藤本 ああ、そうか。だから萩尾さんの作品って、すごく重層的で、わかりそうでわからない。
萩尾 わかっちゃうとね、やっぱりわかる範疇だけの話になっちゃうんです。説明して終わる、っていうんですか。そうするとね、説明が出てくる後についている有形無形のいろんな感情が、ぜーんぶきれいにこっちに寄せられてしまう。でも、人間ってもっとごちゃごちゃしているものでしょう? だから、そっちのほうを追っかけたいなぁ、と。
藤本 萩尾さん自身も、どうなるかわからないっていう所で描いているって感じ?
萩尾 大丈夫。最後は、できてます(笑)。
藤本 でも、どこかそういう所がないと、作品としての膨らみが出ない、と……
萩尾 いや、作品としての膨らみを出すためじゃない。本来、人間は割り切れないものなんですよ。
同じ傷をなぞるということ
藤本 今回、作品を読み直していて、『残酷な神が支配する』って、実は『トーマの心臓』のユリスモールの置かれた立場を発展させたものだな、って気がしたんです。ユリスモールもサイフリートに「翼をもがれた」って言うわけじゃないですか。それは自分の意思を失って屈服させられたっていうことですよね。ジェルミの体験はそれを発展させたもので、背中の傷も、もがれた羽のイメージとつながってきますよね。それは意識されてるんですか?
萩尾 シンプルな言い方をすると、『トーマの心臓』の場合はユリスモールは聖職者になるんですが、ジェルミのほうは、修道院に逃げなかったキャラクターの話です。
藤本 えっ、ユリスモールが修道院に入ったのは、あれ、逃げたっていう話なんですか?
萩尾 (笑)どうしていいか、わかんなかった。
藤本 なるほど(笑)。ジェルミはそこにとどまって何度も傷をなぞっている。 読んでると、人間は治るために何度も同じ傷をなぞるって言うけど、トラウマって何度も反復されて、なんかそこから逃れることができないのかなあ、って。萩尾さん自身は、ある傷を治すために同じ傷を繰り返しているな、と思うところはありますか。
萩尾 うーん。わかんないけど、何度も同じ話、描いてるなって。藤本さんは、どうですか?
藤本 私は自分で自覚してる最初の傷があって、完璧にそれをなぞってる。たぶん、その時とほとんど同じ状況、同じ条件に身を置いて、「今度は、救われた」っていうのをやりたいんですよ。それでずっと、私の恋愛はうまくいかなかった(笑)。でもさすがにもう、煮え湯を飲まされることにも飽きてきたけど (笑)。
萩尾さんもたしかに同じテーマを繰り返し描かれてますけど、繰り返し描くうちに、最初の原点からだんだん変わってくるとか、以前はこだわっていたことが自分にとって問題ではなくなってくるとか、そういうことって、 ありますか?
萩尾 それはないね(笑)。あんまり。
藤本 ない。そうですか。あの、厳しかったお母さんとの葛藤が一番端的に出たのが『イグアナの娘』だと思うんですけど。
萩尾 そうですね。
藤本 たとえば、「表現してしまえば、その問題は半分解決する」とかってよく言うじゃないですか。だから、ああいう象徴的な形の作品を描いたら、何かかが変わるんじゃないかと思うんですけど(笑)、どうなんでしょう。
萩尾 (笑)。 あぁ、そういう意味だったらね。でも私、一時期、理想的な人間関係っていうのにすごい憧れていたんですよ。理想的な家族関係とか、理想的な友人関係とかね。もしそういうのに巡り合えたら、本当に幸福な時間も人生も持てる、と思っていたんですね。
でもね、それは無理だとわかったの。でね、むしろどんな関係であっても人間関係はいつも混迷で、時々ほんの一瞬、いい事があるだけ。それでいいじゃないか、って。「期待するのはやめよう」。それがわかっただけでもよかったかな、と。
藤本 でも、作品の中では相手をなんとか理解しよう、受け止めようという意識がずうっと続いているように思いますけど、違うんですか。
萩尾 あなたなら、大喧嘩した仲の悪い友達と、相手の環境とか、生き方がわかって、仲直りできる?
藤本 うーん、でも、自分とは違っても、どこか底のほうでつながれる感覚っていうのがでてくるような気がしますけど。
萩尾 状況は変わらない。 状況は変わんないわけ。例えば、相手は、相変わらず身勝手だったり。わがままだったり。だけど、その人がどうしてこうなったかっていう過去のいきさつがわかったとして、さあ、仲直りできるか?
藤本 ちょっと変わるんじゃないですか? 変わらないですか、やっぱり。
萩尾 それは、変わらない。
藤本 言い切ってる(笑)。
「やおい」をどう見るか
藤本 ところで、萩尾さんが『11月のギムナジウム』とか『トーマの心臓』とかを、お描きになった時に、私のまわりでは、すごいセンセーションだったんですよ。「こういうものを待っていた」っていう友達が、すごくいて、特別な印象を残していたんですね。とくに、『11月のギムナジウム』が出た時なんか、そうでしたね。
その後、萩尾さんの作品を皮切りにして、少年を主人公にした物語がたくさん出てきて、今、「やおい」とかあるじゃないですか。それで、萩尾さんなんかは、今の「やおい」の状況をどう御覧になっているのかうかがいたいんです。
このジャンルは「もともとは萩尾さんたちが切り開いた」と言われてるけれど、「やおい」と、あの頃の作品って、全然、違うものだ、って感じがするんですよね。
萩尾「やおい」についてはあまり詳しくはないんだけれど、アシスタントさんにコミケでいくつか買って来てもらったんですよ。
で、読むとね、みなさん優しさに飢えているのね。さりげないことで気持ちを慰めてもらう。
たぶんまんがはねえ、ほんとに感情面が描きやすいジャンルなんですよ。文章で書いたり、詩を書いたりするよりも、キャラクターの顔一つ描いて、目でお互い見合うっていうふうに、それだけでも自分の感情が自ずと出てきやすい媒体なわけ。だから、若い人の間で同人誌がすごく流行るんじゃないかなぁ。
藤本 そうだと思いますよ。なにか感情だけじゃない、無意識みたいなものが……。
萩尾 画面から出てきますからね。学校に行ってね、勉強して、こういう学生になんなさい、こういうこどもになんなさい、っていう用意された安全な世界が目の前にある時に、自分の中で一つ一つぶつかる感情を、どう表現したり処理していいのかわからない。だって、たとえば恋愛一つにしても、マニュアルはないですからね。自分で全部考えてやっていく。なにか、そういった感覚の部分が、「やおい」のほうに流れている。それで、若い人に支持されているんじゃないかなと思う。そういうのが、私の「やおい」観。
藤本 なるほど。それから、もう何度も聞かれていると思うのですけども、萩尾さんが、ああいう『11月のギムナジウム』のような少年を主人公とした作品を描こうとしたきっかけというか、動機というかを「やおい」観との比較において語っていただけると……
萩尾 うーん。藤本さんの場合はどうなんですか?
藤本 私の中には、あまり主人公が少年でなきゃいけないというのはないんです。むしろ、 自分っていうものをきちっと持った女の子、っていうのが主人公としては一番好きかな。たとえば『スター・レッド』の星とか。でも、ある時期から先、とくにこの頃の萩尾さんの作品の中に出てくる女の子って、サンドラもそうだしナディアもそうなんだけど、なんか泣くばっかりですよね(笑)。
萩尾 うーん。
藤本 ああいうのは、私は嫌なんですよ。でも、男の子だけがよい部分を持ってるということでもないだろう、っていう感じもあって。私自身、「女であることの重力につかまりたくない」という部分はあるんだけど、逆に女という性を楽しんでいる部分もある。だから、「やおい」にはまってる子たちのように「少年じゃなきゃいけない」っていうのが、実感としてあんまりない。「男で遊ぼう」って感じもあんまりないし。で、萩尾さんは?(笑)
萩尾 私は『11月のギムナジウム』を描いてる時、面白かったんですよ。プロットを作る時に、一応、少女まんがなんだしと思って、女学校の話も作ってみたんです。男子学校バージョンと一緒に。そしたらね、女学校バージョンは、ネチネチしてるんですね。
藤本 ええ。
萩尾 だから、これは男子学校バージョンのほうが面白いと思って。そっちにしたらね、なんか、描いててホクホクしちゃうんですよ。知らない世界だから(笑)。想像力が刺激されるというか。それで、自分でも、描いてて面白いのではまっていったところもありました。で、描きながら思ったのは、あぁ、「女の子はこうしなきゃダメだ」という魔法使いの呪文がね、自分を縛っているんだなぁって。
だからどうしてもね、女性キャラクターを描く時に、なんかねえ、躊躇するんです、色々と。 男のキャラクターのほうがラク(笑)。
藤本 あぁ、そうか。 読者にシンクロしなきゃいけないから。
萩尾 読者というよりはね、ついつい男の人に好かれるキャラクターを描こうとしちゃうんです。こういう名前の女の人は、男の人は嫌いだよね、とか。急ブレーキがかかる。あと、男の子のほうが描いててなんか、解放感が違う。
藤本『X+Y』とか『11人いる!』のフロルとか、両性体で男と女どちらにも変化できる存在をお描きになるのも、やはり同じ動機ですか?
萩尾 そうですね。決まった性がない時、 識は転換する、というのを描きたかったんです。その時、周囲はどう対応するか。『X+Y』の場合は、ちょっと変わったキャラクターにしちゃいましたからね。
進化・世界・双子
藤本 特異な存在って、やっぱり、あんまり性的じゃないんですね。そういう意味では、『ポーの一族』のエドガーもそうだと思うんですけど。あるいは、『銀の三角』とかっていうのもそうですよね。
で、そういったものが時空を越えて続いて行くんだけれども、それがその後、進化の袋小路に入っているみたいなモチーフが、とくにここ十年くらいよく出てきますよね。この世界はすでに終わってしまっていて、「世界は終わってしまったものが見ている夢だ」っていうイメージが、何度も何度も形を変えて顔を出す。失われてしまった世界の影。あるいは進化を夢見るイグアナ。『スター・レッド』の中で必ずしも超能力が「進化」じゃなくて「退化」の一種として捉えられているのも印象的でしたし。
萩尾望都の中で、世界は進化しているのか、退化しているのか。萩尾さんの中では人類は進化の袋小路に入っているという感覚があるんですか?
萩尾 それはよくわかりませんねえ。私は一つ何かわかると、それに対して、そうかなあ、本当かなあ、っていつも考えちゃうんですよ。
たとえば人間は進化してると言われるけど、ほんとにそうなのかな? 理由は何? 言葉が使えるとか、宗教ができたとか、都市を作ったとか、道具を作ったとか、その他には? それはほんとうに進化なの? とかつい考えちゃうんです。
藤本 なるほどね。ところで、萩尾さんは何度も双子について描いてらっしゃいますよね。そして、たしか『MOE』の双子についてのインタビューで、「人が大人になるためには、親殺し、子殺し、そして自分殺しをしなければならない」みたいなことをおっしゃってる。
実際、萩尾さんが双子を描かれる時、全き〈対〉、自分の分身みたいな感じであらわれてくる時と、片方が片方を殺す、みたいな形であらわれてくる時とあるんですけど、それを萩尾さんご自身は、どういうふうに位置づけていらっしゃいますか。
萩尾 双子というのは要するに、鏡にうつった自分、というふうに考えると、その自分が愛しい時と、消し去りたい時と、そのバリエーションのいろんなバージョンを描いてるっていう感じなんですよ。スペアがあるとねぇ、よく見えるんですよ、相手が。だから、自分をうつす鏡としての双子なんですよ。理屈で言えばね。
藤本 それは、今の私ではない本当の私がどこかにあるはずだとか、そういうのではないわけですよね。
萩尾 いや、そうじゃないですね。
藤本 先ほどの世界観にもつながるんですけれど、萩尾さんの世界では窓が象徴的で、「窓の向こうに、私の本当に住んでいる世界があるような気がする」と何かでおっしゃっていたことがありましたよね。その感覚とも共通性がありますか?
萩尾 それとは、全然、違います。つまり、双子の相手っていうのはね、本当に、等身の自分なんです。指導者でもないし、年下の誰かでもない。自分には見えない、自分のある部分なんですね。
藤本 最後にもう一つ。萩尾さんの作品の中には、少年が空を飛ぶとか、少年の背中にある翼、というようなモチーフがよく出てきますね。 私、野火ノビタさんの「やおい」作品である『飛行少年ズ』を読んでいて、あっ、「やおい」の原点にあるのはピーターパンなんだ、って突然思ったんです。あれも家庭から飛び出していった少年の話なんですけど、少女まんがの原点って、色々考えて行くと、家庭の中で生まれた傷みたいなものにあるような気がして。で、そのもとになる近代家族が生まれたのも、この二百年くらいのことで。『ピーターパン』だけでなく『赤毛のアン』だって「メアリーポピンズ』だってそういう背景があってはじめて生まれてくる。そういうファンタジーと、「飛ぶ少年」っていうのが、なんか重なって、つながってくるんじゃないか。
萩尾 それは、面白いですねえ。二百年の家庭の歴史っていうの?「バルザックから小説が始まった」とか言いますし、やっぱり近代都市が人間関係とか、そういうのを作り上げて行く、それの延長線上にあるかもしれないですね。
藤本 ええ。おそらく、それを一番先端的な形でとらえているのが少女まんがで、なかでも萩尾さんの作品じゃないかと思ってるんです。
萩尾 今日は私からもいろいろ聞くつもりだったのに、やっぱりプロのインタビュアーに負けたという感じで(笑)。やっぱり、色々、質問されてしまった。
藤本 いえいえ、今日はどうもありがとうご ざいました。

最新コメント